お知らせー臼井織布
お知らせ
2024.06.16
年間を通じて伊勢木綿を置いていただいている所でです。
最近、伊勢木綿はどこで見れますかと問い合わせが在ります。
沢山見て頂けるのは、弊社(津市一身田)ですが、お近くでご紹介できればと
今後、ご紹介できるところを増やしていきます。
順不同です
(DMでのお問合せはお受けしておりません。)
年中無休
営業時間9:30-17:30
宇治中之切町52, Ise, Mie 5168558
●木金土日11:00〜19:00営業
●webshop以外の商品はDMでお問合せください。
小樽浴衣パスポート @otaru_kimono_pass
中央区南1条西5丁目6-3 CUTEビル2F, Sapporo-shi, Hokkaido, Japan 060-0061
玉川3-28-2 ハイツリバーサイド101, Setagaya, Tokyo 1580094
https://otsuka-gofukuten.com/
大塚呉服店京都
11:00-19:00 (定休日なし)
京都府京都市東山区星野町88-1
大塚呉服店神戸
10:00-20:00(元日のみ休業)
神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急4階
上りエスカレーター前直進
着物好きの方々と繋がり、普段キモノのこと、もっと知りたいです。
当アカウントでは、新入荷商品のお知らせ、コーディネートのご紹介などをお届けします。
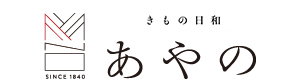
〒516-0026
三重県伊勢市宇治浦田1丁目5-6
フリーダイヤル:0120-454-865
TEL:0596-26-1177
https://kimono-ayano.jp/
株式会社晴レノ日スタヂオ 瀬戸口ゆうこ 〒111-0036 東京都台東区松が谷2-27-3-101 電話&FAX 03-5246-4065 携帯 080-3245-4924 Mail info@harenohistudio.com HP: http://harenohistudio.jp/
会社名 有限会社 ゴフクヤサン・ドットコム 代表者 取締役 居内久勝 本社所在地 大阪府大阪市中央区船場中3丁目船場センタービル7号館228(2階南側) 【実店舗:同ビル 7号館 B1北側】 電話番号 06-6251-6611 設立 2002年8月8日 (前身:居内商店創業1965年) 事業内容 呉服卸、小売業 取引銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 ゆうちょ銀行 沿革 1965年4月 (前身:居内商店創業)
https://store.gofukuyasan.com/
伊勢木綿のレンタル着物
&着物リメイク服「きもも堂」
| 名称 | 合同会社Kimomo堂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒519-1112 三重県亀山市関町中町463-3 |
| TEL | 090-9915-9158 |
| info@kimomodo.com |
https://peraichi.com/landing_pages/view/kimomodo/
Shop ギャルリー・ノン galerie non
〒167-0042
東京都杉並区西荻北4-3-4 美光弐番館101[google map]
TEL&FAX 03-3394-5670
URL:http://www.batta.co.jp
e-mail:non@batta.co.jp
Access
JR中央線・総武線西荻窪駅北口『伏見通り』徒歩5分
定休日 月曜日
OPEN 13:00~19:00
◇現在は夫婦二人でお店をしています。
◇8歳5歳1歳育児中
◇毎日着物を着る私達のセレクトする商品をご紹介
島根県松江市竪町86-1
TEL 0852-21-4881
定休日 日・月・祝
ウェブショップは下記をご覧下さい
竪町86-1, Matsue, Shimane 690-0052
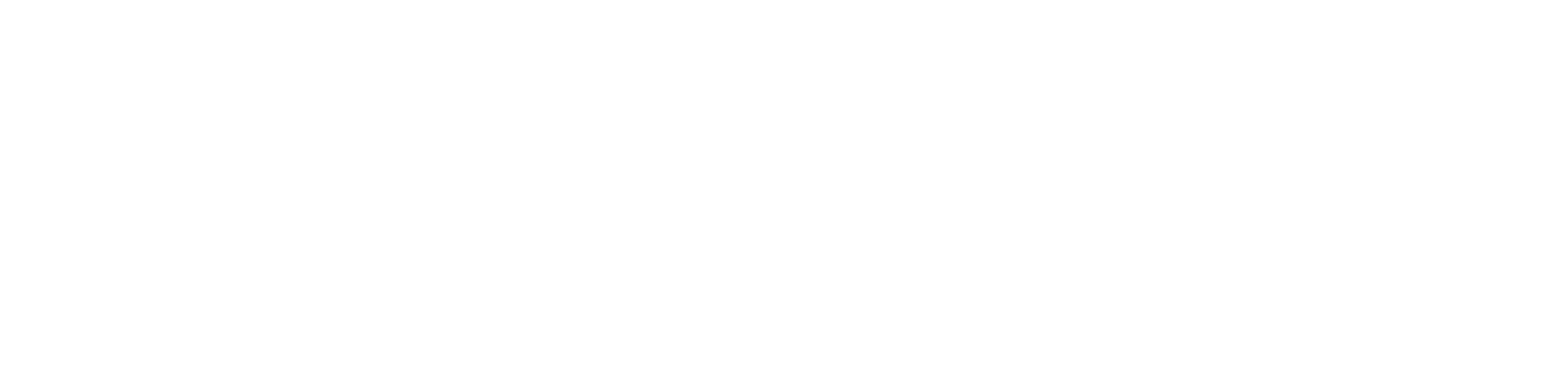
会社名
株式会社岡野
所在地
[本社工房] 〒811‒1204 福岡県那珂川市片縄東1‒6‒21
創業
1897年 明治30年
役員
代表取締役社長 岡野博一
事業内容
着物・染織品の制作販売
きぬのや年間を通じて伊勢木綿を置いていただいている所でです。
最近、伊勢木綿はどこで見れますかと問い合わせが在ります。
沢山見て頂けるのは、弊社(津市一身田)ですが、お近くでご紹介できればと
今後、ご紹介できるところを増やしていきます。
順不同です
おかげ横丁 神路屋
伊勢神宮内宮の門前町にある「おかげ横丁」の和雑貨を中心としたお店です。御朱印帳もたくさんございますので、参拝前に是非お越しくださいませ。
(DMでのお問合せはお受けしておりません。)
年中無休
営業時間9:30-17:30
宇治中之切町52, Ise, Mie 5168558
www.okageyokocho.co.jp/tenpo/kamijiya
臼杵 美紀 キモノハナおあつらえ
usukimiki
ショッピング・小売り
札幌・大通の小さな着物屋。
●木金土日11:00〜19:00営業
●webshop以外の商品はDMでお問合せください。
小樽浴衣パスポート @otaru_kimono_pass
中央区南1条西5丁目6-3 CUTEビル2F, Sapporo-shi, Hokkaido, Japan 060-0061
モダン着物小物 梅屋
umeyakimono
衣料品(ブランド)
自分らしく、自由に、おしゃれに着物を楽しみたい方のための、カジュアル着物と小物のセレクトショップです。オリジナル商品多め。ネットショップがメイン。1人でやっているため、実店舗(二子玉川)/オンライン接客は、前日までに予約サイトより
玉川3-28-2 ハイツリバーサイド101, Setagaya, Tokyo 1580094
umeyakimono.com + 1
https://otsuka-gofukuten.com/
大塚呉服店京都
11:00-19:00 (定休日なし)
京都府京都市東山区星野町88-1
大塚呉服店神戸
10:00-20:00(元日のみ休業)
神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急4階
上りエスカレーター前直進
obebehohoho
おべべほほほの公式ビジネスアカウントです。
着物好きの方々と繋がり、普段キモノのこと、もっと知りたいです。
当アカウントでは、新入荷商品のお知らせ、コーディネートのご紹介などをお届けします。
obebehohoho.square.site

〒516-0026
三重県伊勢市宇治浦田1丁目5-6
フリーダイヤル:0120-454-865
TEL:0596-26-1177
https://kimono-ayano.jp/
株式会社晴レノ日スタヂオ
瀬戸口ゆうこ
〒111-0036
東京都台東区松が谷2-27-3-101
電話&FAX 03-5246-4065
携帯 080-3245-4924
Mail info@harenohistudio.com
HP: http://harenohistudio.jp/
会社名 有限会社 ゴフクヤサン・ドットコム
代表者 取締役 居内久勝
本社所在地 大阪府大阪市中央区船場中3丁目船場センタービル7号館228(2階南側)
【実店舗:同ビル 7号館 B1北側】
電話番号 06-6251-6611
設立 2002年8月8日 (前身:居内商店創業1965年)
事業内容 呉服卸、小売業
取引銀行 三井住友銀行
三菱UFJ銀行
ゆうちょ銀行
沿革 1965年4月 (前身:居内商店創業)
https://store.gofukuyasan.com/
伊勢木綿のレンタル着物
&着物リメイク服「きもも堂」
名称 合同会社Kimomo堂
所在地 〒519-1112
三重県亀山市関町中町463-3
TEL 090-9915-9158
Email info@kimomodo.com
https://peraichi.com/landing_pages/view/kimomodo/
Shop ギャルリー・ノン galerie non
〒167-0042
東京都杉並区西荻北4-3-4 美光弐番館101[google map]
TEL&FAX 03-3394-5670
URL:http://www.batta.co.jp
e-mail:non@batta.co.jp
Access
JR中央線・総武線西荻窪駅北口『伏見通り』徒歩5分
定休日 月曜日
OPEN 13:00~19:00
えんや呉服店
enya_gofukuten
◇お茶所島根県松江市の創業70年の呉服屋
◇現在は夫婦二人でお店をしています。
◇8歳5歳1歳育児中
◇毎日着物を着る私達のセレクトする商品をご紹介
島根県松江市竪町86-1
TEL 0852-21-4881
定休日 日・月・祝
ウェブショップは下記をご覧下さい
竪町86-1, Matsue, Shimane 690-0052
matsue-kimono.com/free/shoukai

会社名
株式会社岡野
所在地
[本社工房] 〒811‒1204 福岡県那珂川市片縄東1‒6‒21
創業
1897年 明治30年
役員
代表取締役社長 岡野博一
事業内容
着物・染織品の制作販売
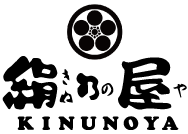
佐賀市卸本町にある、お洒落きもの館「絹乃屋」
0952-31-7411
https://kinunoya-saga.com/

2024.06.16




2024.02.18
先日仕事で、伊勢の方へ行ったとき気が付きました。
大きく宣伝していただいていました。感謝


2024.02.18
諸般の事情により、値上げをします。
去年の年明けから、たかが木綿と思い諸物価(糸代等)値上げラッシュでしたが、じっと我慢をしてきました。しかし、毎月末に厳しくなって取引先を含めいろいろとご相談した結果値上げという事となりました。今前の織り方の物は、より魅力的に。又最近の夏の暑さは尋常でなく、桜の時期から紅葉の直前まで着ていただけるような生地を現在考慮中で、より楽しく来ていただけるような柄行きを考えています。


2023.12.09
昨今の、物価上昇による値上げラッシュに疲弊しております。
長年木綿屋をやっておりましたゆえ、短期の値段の上がり下がりで驚くことはあまりないようにしておりましたが
ちょっとひどすぎると思い、色々考えてみました。
弊社が製造しているのは、昔ながらの木綿です。経糸緯糸とも弱撚糸のこだわり今ではそれができるのが少なくなってきたと
感じています。(手織りでさえ経糸に強撚糸を用いるのが普通になってきました)
また、織機も明治三十八年式織機を使用して昔の風合いを大事にしています。
こだわりの、最大の理由は風合い手触り、着心地、使用感だと思います。
先祖から言われてきたことを、寡黙に守ってきた故世の中がどんどん変化して進んでいても下を向いて
仕事をしてきました。今までいろんな困難に会いました。近くにあった染屋さん綛繰り屋さんの廃業。
織物協同組合の解散、繊維試験場の解散、日本橋の木綿問屋の数々の廃業、取り込み詐欺に引っかかる。
特に販売先の廃業、夜逃げが厳しかったです。
その様な中、じっと下を見てやってきました。
幸にも、京都の着物関係の問屋さん、SOU SOU さんをはじめとするデザイン会社、先代からのお付き合いのある
会社さんからこれをやってもないか、あれをやってみないかとご指導を受け、採算は合わないことが多いですが
何とかやってきました。
しかしここ最近の、気候変動に始まる社会の大きな変化、日本人として育ててきた文化が大きく変わってきたことを
実感します。単に年を取って社会の変化についていけなくなっただけかもしれません。
そういうもろもろの変化に、伝統的な木綿も変わってゆく、若しくは進化していかねば
残らないと思い、実験を重ね提案してゆきます。
画像は、最近のポシェットです。伊勢福の神路屋さんで販売していただきます。
考え方は、同じ柄の組み合わせは作らない。持っていて楽しい。使い易いなど
常にご指導をいただき切磋琢磨して店頭にあった時に手に取っていただければと努力しております。
店主敬白

2023.11.19
この前、見学者さんからどこで色糸を買っているのですかと、質問を受けました。
業者の関係者だったので、ある程度は理解されていると思っていましたが同業屋がほとんどいない、知名度はないので弊社の先祖が昔織っていた物を復元しているだけだと言っているので判っていただけると思っていたのですが。
すべて、色糸は自社の企画です、又柄もそうです。江戸時代末期、明治大正昭和初期の織物業が元気なころに織っていたものです。
そして柄立ては、綛染めの糸を使い、屏風を使用して部分整経です。

目いっぱい使うと画像のようになります。


使う糸も綿を数回撚っただけの単糸を使用しています。ので、経糸には綛の糊付けをしています。最近経糸には撚糸を使うところがほとんどです。手織りでも撚糸を使われていると聞いています。何のための手織りか判りませんが。よって、風合い、手触りは最高です。
乾燥すると、しょっちゅう経糸は切れます。

根気よく、毎日織っていますが見学に来られた方は38年式の明治の機械で織っていますと言っても、なかなか理解されていません。
昔の機屋さんをやっておられた方は、まだやっておるのかと驚いています。
それと毎日掃除をしています。色物を織りますので、白物に綿が飛んで行ってキズになります。白物だけを織っていればあまり気に成らないです。
良く見学に来られた方に説明するのですが、機械の修理は自分でします。38年式だと部品が軽いですが、G型になると専属の手直しさんか、修理専門の業者の方が必要です。構造が簡単で部品が軽いのですべて自分で修理しています。なかなか信用していただけません。毎日使うのでしょっちゅう壊れます。ほとんど、明治のころの構造、部品を使っています。特に、父は商学部出身だったので金属の焼き入れに関する知識が無かったゆえ、フィラーは、針金を曲げて使っていましたが今の部品は焼き入れをして頂いていますので、糸が当たった程度では変形しません。基本的な材料工学、機械工学の知識があれば、それほど難しくはありません。







.JPG)





